BlogTop > Archives > 2008年9月 Archive
2008年9月 Archive
« 2008年8月 | 2008年9月 | 2008年10月 »
- Firefoxアドオン、ステータスバーの整理にOrganize Status Bar 28日
- 今月のいらんことしい(2008年9月) 27日
- 背景用ストライプ画像4種 23日
- メモ:コメスパ対策とか 23日
- 訂正:ActionStreamsプラグイン、Deliciousのfeedについて 19日
- メモ:HTMLのコメントのつけかたなど 15日
- 記事投稿者によるコメントのときおよび返信コメントにclass属性 13日
- メモ:My WILLCOMに2台目の通信機器を登録する 10日
- テンプレート入れ替えとその顛末 09日
- 普段使ってるフライパンで作るだし巻きたまご 07日
- [お知らせ]RSSフィードで記事概要の配信に変更しました 06日
- [MT]テンプレートタグリファレンスへのリンクを張りやすく 06日
- EntryCategoriesタグを改良するプラグインを使ってフォルダ一覧のリストを表示 01日
Firefoxアドオン、ステータスバーの整理にOrganize Status Bar
- 2008年9月28日 18:25
- Last update: Apr 30, 2014 12:09
- net

Firefoxでアドオンをいくつか入れていると、ステータスバーに導入中のアドオンのアイコンが並んできます。Organize Status Barはこれを表示させたり非表示にしたり表示順をいれかえたりするとこのできるアドオンです。
この前、たまたま見たページでなのですが、どういったアドオンなのかわからないけど、キャプチャでGmailのアドレスがステータスバーにでてしまうものだから、その部分にモザイク処理などされています。
@ITの以下の記事です。
そこまで加工するのなら、ステータスバーを非表示にしてからキャプチャ撮るとか、必要な箇所をトリミングでもしたらいいのではないかなと思うわけで。
また、ステータスバーなどにライターさんの使ってるアドオン群が多く並んでいるのをみると却って引いてしまったりします。#アドオン記事と関係ないし、みたいに。
ま、自分が思ったことは自分で実践してたらよいだけの話でして、(自分が)キャプチャ撮るときは少し気を遣いたいなというお話でした。
さて、こんな場面でも「Organize Status Bar」を使いますと、ステータスバーに表示させたいアドオンなどコントロールできますので便利そうです。
アドオンは以下のページから
設定画面は下のような感じです。

- Comments
- TrackBack Closed
今月のいらんことしい(2008年9月)
今月(2008年9月)サイト内でカスタマイズした箇所を中心にまとめておきます。
- テンプレートをVicuna2.2.0に
- Yahoo!検索カスタムサーチを試した
- ActionStreamsのブログのテンプレートをシンプルに
- MyBlogLogのAbout Me Widgetを使ってみた
- (追加) RebuildIndexFilter プラグイン(簡易版)を導入
今月は、本ブログでは、テンプレート差し替えくらいで、あとは、どうでもいいような箇所に手を入れたという感じです。
Yahoo!カスタムサーチですが、いくつかのステップを経て簡単に自分のサイトに合ったカスタム検索窓用のコードを作成することができます。
ためしにサイトトップページほかにつけてみました。(作成にはYahoo! JapanのIDが必要になります)
ActionStreams(maRkのActionStream)は、前からページをシンプルなものにせしめんと欲し(謎)、思い切って簡単な構造のテンプレートにしてみました。色気を出してjQueryを使って開閉するようなものにしてみました。同時にこれまで、ページをcronジョブで再構築してたものを手動で再構築するようにに切り替えました。あまり頻繁に見にこられているページでもなかったですし。(汗
jQueryのアコーディオンについては以下のページを参考にしました。
MyBlogLogのwidgetにはいくつか種類があり、いままでRecent Readersという、俗に言う「あしあと」みたいなものを作ってページに貼っていましたが、今回作ってみたのが、「About Me Widget」というものです。こちらのWidgetは自分のMyBlogLogのプロフィールページのリンクや、利用してるサービスとかサイトのリンクなどが表示されます。
また、好みのデザインに変えることも可能です。Widgetを作成する場所ですが、Recent Readersとは別でプロフィール編集のところからとなっていました。
【追記】RebuildIndexFilter プラグインの簡易版(RebuildIndexFilter Lite)のほうを導入しました。カスタムインデックスページがいくつかあるのと、フォルダ一覧のリストを作成した関係です。
- Comments
- TrackBack Closed
背景用ストライプ画像4種
利用させていただいてるテンプレート(Vicuna)の背景画像ですが、これまでここで使ってきた画像4種類ほど紹介。
ここしばらく、vicunaスキンのBoomarを使わせていただいているのですが、背景画像を月替わりで入れ替えとかして使っています。
たまに模様替と思いつつも、急にデザインがかわるのもアレかとおもってさりげなく背景画程度なら変更してもまあいいか、というおもいつきだけで背景画像を入れかえるようにした次第。
とはいえ、生憎、画像をデザインできるほどの技能を持ち合わせておりませんので、画像のカラーパターンを違えてみるということでやっていました。
で、今回いくつか出来上がりましたので、公開したい欲求とでもいいましょうか、そんな感じでこの記事にて4種類披露させていただきます。
以下の4タイプです。色彩センスが乏しくてお恥ずかしいですが。

4種まとめたファイルをこちらにておいておきます。ファイル名の最後のほうに薄いほうのカラーコードをお節介ながらつけてあり(例:xxx-999999.gif)、背景のbackground-colorにこれを指定なぞするといいかな、といった感じです(背景画をかえておきながらデフォルトのbackground-colorのまま使っているというのはナイショだ)。
- Comments
- TrackBack Closed
メモ:コメスパ対策とか
- 2008年9月23日 09:57
- Last update: Sep 23, 2008 17:24
- myown

コメントスパム対策とおよびゲストブックへのスパム対策などについてです
ここのブログでは、MT4を使って以来、プラグインによるスパム判定を受けたコメントはみたことがありません。それもCaptcha効果なのかどうかわかりませんが。
ただし、正確にはスパムをまったく受けとっていないとは言い切れない部分もあります。といいますのも、サーバのログをみますと、特定記事等で海外からと思われるIPアドレスからのPOSTをいくつか見ることがあるからです。
さて、Googleのウェブマスター向けのドキュメントには、コメントスパム対策について以下のページにて紹介がなされています。
上記ページより、各セクションのタイトルのみ抜粋します
- コメント スパムを防ぐ方法
-
- スパム対策のコメント ツールを使用する
- コメントの管理機能を有効にする
- 「nofollow」タグを使用する
- コメント内のハイパーリンクを許可しない
- robots.txt またはメタ タグを使用してコメント ページをブロックする
- ゲストブックまたはコメントを有効にする際は十分に検討する
スパム対策のコメント ツール
は、当ブログにおいては、「CAPTCHA」をブログ開始当初から導入してまいりました。また、TypePad AntiSpamプラグイン導入も4.1xの時分よりおこない、4.2以降同梱されており、そのまま引き続いて利用しています(いまのところ、TypePad AntiSpamでスパムがブロックされたという数値はないようです*)。
コメント管理機能について。ここの部分は少し迷っていて、今の時点ではコメントについては認証はおこなってません。のちの設定変更などに備え、サインインしてコメントをいただいたかたについては、管理ページからあとで承認するようにしています。
* TypePad Antispamをいれると、管理ページトップのウィジェットにブロックしたスパムの数が表示される。その数値が0ということ。
ゲストブックとスパム対策
ゲストブックにおけるスパムの問題は、ゲストブックページを設置するようになってからここでもスパムを受けとっていたようです。MTのシステム上ではわからないのですが、サーバのログを見た限りでは、ゲストブックのページにアクセスしたのち、直接コメントのCGIにアクセスしているようでした。
ということで、ゲストブックページは特定のフォルダにいれて隔離させ、とりあえず海外からのアクセス制限という形をとっていました。
最近では、ナビゲーションリンク内にリンクを張るのもやめました。これは単に何のためのページなのかわかりにくいので、寧ろコメント欄のほうに添え書きしてあったほうがよいのではないかと思ったためです。
robots.txtで検索にあがらなくするという方法は、このドキュメントではじめて知りました。
.htaccessによる規制
XREA&CORE SUPPORT BOARD内にて、「POST」リクエストを.htaccessにて制限するための.htaccessファイルが紹介されています。
海外からのPOSTを規制するというものです。海外からのユーザーで問題ないかたのコメントも弾いてしまいますが、国内でしかコメントのやり取りがないようならばこれもかなり有効かと。
- Comments
- TrackBack Closed
訂正:ActionStreamsプラグイン、Deliciousのfeedについて
リニューアル後のDeliciuousのフィードで、RSS2.0が拡張されているようで、エレメントが以前のものと変わっていたもよう。これに従い、ActionStreamsのconfigファイルを修正してみました
前に、DeliciousリニュにつきActionStreamsのconfig.yamlを修正で紹介したのですが、その後確認しましたところ、feeds.delicious.comより配信されますフィードで、POSTされた時間をあらわすエレメントが、以前のフィードと変わっていたために、そのままで使うと、時系列の情報が正しく反映されません。例えば、プロフィールの画面からActionStreamsの一覧をみることができるのですが、Deliciousのところだけ投稿時間が「○時間後」といった表示になっていたりしてました。
Feedを確認したところ、投稿時刻を示すエレメントには、「pubDate」を使っているようでしたので、修正したconfig.yamlは以下のようになります。created_onの次をpubDateにしておきます。修正が済んだら、サーバのほうに上書しますが、念のためにconfig.yamlのオリジナルファイルはローカル側で残しておくといいかと思います。なお、config.yamlの改変は自己責任にてお願いします。
action_streams:
delicious:
・・・ 途中省略 ・・・・
url: 'http://feeds.delicious.com/v2/rss/{{ident}}'
identifier: url
xpath:
foreach: //item
get:
created_on: pubDate/child::text()
ちなみになのですが、ActionStreamsのオリジナルのconfig.yamlに記載されているdeliciousのフィード(http://del.icio.us/rss/(user))でアクセスすると、リダイレクトされて、ワタくシの場合ですと以下のようなURLです。v2というディレクトリがつくかつかないかですが、こちらの場合はRDFによるメタ情報といった感じRSS1.0です。dc:dateを使っているので、オリジナルのままで上記のような修正は必要なさそうです。どちらを選択するかは、各自の判断でといったところでしょうか。
- http://feeds.delicious.com/rss/maR_K
- Comments
- TrackBack Closed
メモ:HTMLのコメントのつけかたなど
HTMLのソース中に書くコメントについて、目にとまったサイトなどをメモしておきます
正しいコメントの書き方をしましょうということで(自戒もふくめて)。コメントについての解説は以下のサイトにて。
コメントの中身にハイフン(-)が続いてしまうのはマズいというのはおぼえておきたいと感じました。
鳩丸よもやま話のページには、正しい書き方であっても、ブラウザの独自の判断により正しく認識してくれないケースを「ぶったぶたれた
」という例で紹介されています。注釈宣言テストというページがあり、Firefox3でみたところでは、問題なく表示されていました。さて、IE6でみると・・・・・・
Open MagicVox.netさまでは、(X)HTMLの終了タグへのコメントのつけ方を紹介されています。
これは、なるほどと思いました。少し気になったんですが、それは、HTMLでタグが入れ子になるときが割りとあって、Vicunaテンプレートでもそうですが、タブインデント(スペースでもいいんですけど)を利用して整形などしているときにはどうかな、という部分です。
ま、いらんことで特に意味はないんですが、簡単なXMLでコメントの書き方だけためしてみました。ブラウザで、ドキュメントツリー表示でみたところ、「構造上もコメントの所属が明確
」という点については、納得できた気がします。そのあたりは、好みの部分もあってアレですけど。
<?xml version="1.0"?>
<root>
<main>
<title>hoge hoge
<!-- description element --><description>hoge^2</description>
<!-- end title --></title>
<!-- end main --></main>
<!-- end root --></root><?xml version="1.0"?>
<root>
<main>
<title>hoge hoge
<!-- description element --><description>hoge^2</description>
</title><!-- end title -->
</main><!-- end main -->
</root><!-- end root -->- Comments
- TrackBack Closed
記事投稿者によるコメントのときおよび返信コメントにclass属性
コメンテーターが記事投稿者である場合や記事投稿者が返信コメントしたときならびにゲスト投稿者が返信コメントをしたときclass属性を付与するというのを試してみました
コメントの種類を分ける
Movable Typeのシステムが受けとったコメントの種類を分類してみます。色々なわけ方があるかと思うのですが、ここでは、コメンターが記事作成者なのかそうではないのか、というところに重点を置いて、起こり得る事象で分けてみます。
*記事作成者以外のコメンテーターをここでは便宜上「ゲスト」としておきます
コメントの返信機能を利用していない場合
- ゲストによるコメント
- 記事作成者によるコメント
これに対して、コメントの返信機能を利用した場合、コメントの種類が少し増えて以下のようになります
コメントの返信機能を利用している場合
- ゲストによるコメント
- ゲストが誰かのコメントに返信したコメント
- 記事作成者によるコメント
- 記事作成者が誰かのコメントに返信したコメント
コメントの種類によってclass属性を与えることを具体的にまとめると以下のようなものです。
クラス名などはこちらで適当につけたものなので適宜かえたらよいかと。
- 返信コメントには、class="comment-reply"
- 記事投稿者がコメントしたとき、class="entry-author"
- 記事投稿者が返信コメントした場合はclass="comment-reply entry-author"
コメントのテンプレートの書き換え
MT4.2のデフォルトテンプレートの例で説明します。コメント返信の機能を利用しているものとして
コメントのテンプレートモジュール(comments.mtml)から以下のようなコードの行を探します。
<div id="comment-<$mt:CommentID$>" class="comment<mt:IfCommentParent> comment-reply</mt:IfCommentParent>">
コメントが記事投稿者である場合は、MTIfCommenterIsEntryAuthorというテンプレートタグを使ってclass属性を付与してみます。
<div id="comment-<$mt:CommentID$>" class="comment<mt:IfCommentParent> comment-reply</mt:IfCommentParent> <MTIfCommenterIsEntryAuthor> entry-author</MTIfCommenterIsEntryAuthor>">
*横に長くなるため途中改行しています。
あとはスタイルシートでお好みのスタイル指定でカスタマイズすれば、コメントの状態の表現が可能ということになります。
実際におこなってコメント欄にも付与されたクラス名を出力させてみた結果を以下のキャプチャにて示します。
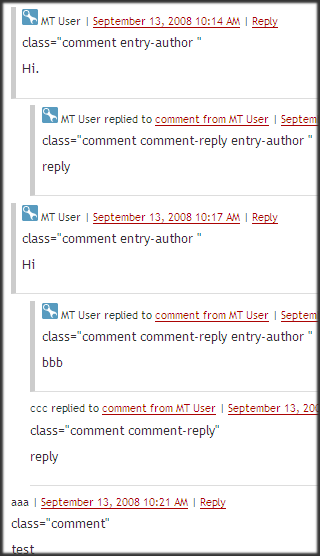
ここでのカスタマイズでは、単にclass属性の属性値を複数与えることでスタイル分けしようとする(#なんちゃってスレッド風みたいな)ものですが、構造的にコメントを階層化したいときはMovableType.jp の以下の記事が参考になります。
- Comments
- TrackBack Closed
メモ:My WILLCOMに2台目の通信機器を登録する
- 2008年9月10日 20:07
- Last update: Jun 21, 2013 17:57
- mobile

ウィルコムで1台あとで端末を買い足したりして、かつ既存の請求先に統合して支払いをおこなっている場合に後から買った機器の情報をMy WILLCOMに登録させたときのメモ
ウィルコム製品を買ったお店で聞いたら教えてくれそうな内容ではあるのですが、こちらから聞かないと教えてくれなそうなのでメモしておきます。
追記:2013年6月20日に新たにMy WILLCOMがリニューアルオープンされました。このページでは、旧My WILLCOMのページでの説明をしています。なお、旧 My WILLCOM ページは、2013年9月末をもって運用を終える予定のようですので、このページの情報も一旦凍結という形とします。(詳細: https://store.willcom-inc.com/ec/faces/member/enter.jsp および、http://www.willcom-inc.com/ja/support/mywillcom/change/index.html)
ケースとしては、前にウィルコムの電話機を購入して、あとからデータ通信カードを買い足した、もしくは逆にデータ通信カードを持っていて後からウィルコムの電話機を買った場合で片方しかMy WILLCOMに機器を登録してなかったという場合です。
なお、以下の内容は自分のおこなった状況に基づいていますから、もしかすると人によっては当てはまらない部分もあるかと思います。あくまでも参考程度のものです。
My WILLCOMの登録が済んでいるものとして。
- まず必要な情報が控えてあること(登録したい通信機器のウィルコム電話番号・暗証番号)
- My WILLCOMにログイン
- 電話通信機器の登録のリンクから登録画面にいく
- 必要な項目を入力して、「確認する」のボタンを押す
流れはだいたい上記のようなものです。データ通信カードの場合は、購入したときに電話番号が何番ですよ、と教えてくれないことがあるようです。データ通信カードの電話番号は購入の際の契約申込書の上部に070から始まる番号で記載されています。暗証番号は申込書に書いた4桁の番号になります。
登録情報の変更の手続きが済むと、My WILLCOMに登録したメールのほうにその旨のお知らせが届きました。
確認は、「ご契約情報照会・変更」のリンクから。あと、購入時に請求先を統合するように申し込んだのであればMy WILLCOM側で請求先を統合するような設定をおこなわなくても照合されていて大丈夫なようです。請求照会サービス(*利用には申込がいります。手続きはMy WILLCOMで可能。←サービス拡充される前での話です。サービス拡充実施後は請求照会サービスに申し込む必要はないもよう。詳細は下に示しましたWillcomのページ参照ください)のところで電話番号が複数でていれば正常な状態かと思います。
あと、請求照会サービスが来月(2008年10月)からサービス拡充がおこなわれるとのことなので、ここでもメモしておくとします。
- Comments
- TrackBack Closed
テンプレート入れ替えとその顛末
Vicunaのテンプレートを、MT4.2(4.21)に対応すべく、既存のものに追加する形で入れ替えしました。結果とそのなかでおこったことなどを
カスタマイズが多いということ
MTのバージョンも4.2になったことなので、テンプレートもmt.VIcunaにかえてみようとおもいました。で見た感じだとわかりにくいのかもしれないけど、ここではわりとテンプレート弄ってるものだから、元の姿とだいぶ変わってる箇所があります。
手順どおりでmt.Vicunaのテンプレートセットを入れ替え作業をするときにこちらが困る点はというとこれ。
- 手順どおりにテンプレートセットを丸ごと変えてしまうと、これまでに作ったカスタムテンプレートが消えてしてしまう
テンプレートセットでの入れ替えは、手軽で簡単におこなえるし、クリーンインストールという意味ではいいのかも知れないんですけど、カスタムテンプレートが多いとそこからもとの状態に近づける作業時間が追加されることになるです。
そのために、一部テンプレートだけ差し替えをおこなってテンプレートの初期化をするという方法もあるわけですが、これもカスタマイズの箇所が多いと差分をとったりするのも結構手間だったり。でもまあ手間かけずに済まそうというならデフォルトのまま使えよ、とかいわれそうなんですけど。
テンプレッツプラグイン使ってみる
このようなときに、もしかして救世主?とおもったのが、Templetsプラグインなんであります。なお、プラグインについてはOgawa::Memorandaさまの以下のページを参照します。
このプラグインを使うことで、必要なものを既存のものに追加という形がとれますから、自分がカスタマイズして追加したテンプレートを残したまま、新しいテンプレートを追加することも可能となります。
入れ替え作業は難航?
それで、アーカイブリストのテンプレートとウィジェットを追加することをまずはやってみました。
おこなう前にcofig.yamlファイルの書式を理解する必要があって、これを理解するのに少し時間かかってしまいました。ローカルでテストしてたら、YAMLファイルが正しくないためにシステムがエラー返してましたし。(汗
あと、いきなり表示崩れとかやってしまいました。それは前のテンプレートでDIV要素が途中で切れる形になってモジュール化されてた箇所が原因で、当方がその部分すっかり忘れてたんですね。
結果として、テンプレッツの追加そのものはうまいことできました。ただ部分的なテンプレートの構造がわかってなかったためにヘマしてただけでした。
おわりに
教訓として、テンプレートを差し替えるときは、中身をそっくり替えてから、バックアップされたファイルなどを戻すほうが無難そう。あと、自分が弄った箇所が後からわかるようにメモに控えておくか、差分が取り易いようにカスタマイズをおこなったあとでローカルにファイルとしてとっておくのもいいかも。それと、テンプレートのコピー機能とかもうまく使いたいかな。
- Comments
- TrackBack Closed
普段使ってるフライパンで作るだし巻きたまご
- 2008年9月 7日 10:30
- Last update: Mar 05, 2012 10:44
- myown

だし巻きとか厚焼きたまごを作るときに、いつも使っているまるいフライパンで作っています。普通のフライパンでたまご焼きを作るのに自分にとって何がひつようかをメモ
まずここでの内容は根拠もない自分はこうという点でまとめてます。たまご焼きの作り方のコツについては、以下の記事など参考にしたいところです。
さて、フライパンの形状がまるいことでの制約される点は以下
- 巻くと、両端の厚さが中央に比べて薄くなる
- フライパンの直径が広いと横幅が長いために、たまごの量が少ないと厚く巻くことができない
上記を妥協できれば、玉子焼き器でなくてもフライパンでも十分かと。家庭の料理なのでなんでもありということで。
気をつける点をまとめると
- 一回で焼くたまごの量は3個くらいから
- フライパンはよく熱して焼くときは強火のまま
- たまごを流すときできるだけフライパン全体にのばさず、一回目に巻いたたまごの長さにあわせてたまごを流す
- だしの量が多すぎると巻きにくい
- 焼き終わったら、ラップに包んで形を整える
薄焼きたまごを作るとにみたいに、フライパンの周りにたまごを伸ばさなず、流したら早めに巻いてしまうのがポイントです
追記:2009/03/11 実際に焼いてラップをかけた状態の写真を載せておきます。

- Comments
- TrackBack Closed
[お知らせ]RSSフィードで記事概要の配信に変更しました
このブログのフィードでRSS(2.0)のほうを記事の概要で配信する形に変更いたしました。
先ほど変更させていただきました。Atomフィードでは引き続き全文を読むことができるようになっております。
すでに一部のページでは、link要素による、RSSのオートディスカバリーを表示させないようにしております。また、サイドバーメニュー内のFeedsの項目もAtomフィード1つにして、RSSはmetaの項目へ移動しました。
概要への変更はテンプレートでMTEntryBodyとあるのをMTEntryExcerptに変更するというだけです。因みにここのブログでは、殆どの記事で先頭の段落=記事概要という形式になってます。あと、概要配信につき記事に続きがあった場合でもメッセージが表示されないように、これまでの記述を変更しました。
この件とは別にお詫びです。テンプレートを少し手直している関係で、一部のページで表示がおかしくなっていたりすることがあります。m( _ _ )m
- Comments
- TrackBack Closed
[MT]テンプレートタグリファレンスへのリンクを張りやすく
- 2008年9月 6日 00:44
- Last update: May 24, 2016 07:46
- MovableType

Movable TypeのタグリファレンスのURLがわかりやすい形になったようです。ということで、ブログ記事編集画面からでもタグリファレンスへのリンクを簡単に貼れる様にCustom Editor Buttonプラグイン用のボタンを作ってみました
タグリファレンスのリンクについては、MovableType.jpで以下のように説明があります。
URL の https://www.movabletype.jp/tags/ までは共通ですが、そのあとのタグ名は、頭の MT が抜けても、mt: という表記でも、全体が大文字でも小文字でも、それらが混ざっても、そのタグがあればリファレンスページに移動できます。
わかりやすい URL でタグリファレンスを参照できるようになりました
ということで、CustomEditorButton2 (blog.aklaswad.com)用にボタンを作ってみたり。
バージョン0.3で動作確認はFirefox3.0でしかおこなってません。config.yamlに書くソースは特に面倒なことはしてなくこんな感じで
buttons:
tagreflink:
image: images/tagref_link.png
title: TagReference
code: |
function ceb_tagreflink ( text ) {
var mttag = var mttag = text.replace(/^mt\:?/,"").toLowerCase();
return '<a rel="tag" href="https://www.movabletype.jp/tags/' + text + '">' + text + '</a>';
}
あまり需要はなさそうですけど、リファレンスページへ確認にいかなくてもリンク張れたりするのがいいかなといったところです(スペルミスには注意ですが)。
一応、Firefoxアドオン、Make Link用にも書いていてこんなです。リファレンスページから簡略化されたリンクに直したいようなときに
- 名前:
- MTTagReference
- フォーマット:
- <a href="https://www.movabletype.jp/tag/%text%">%text%</a>
- HTMLエンティティを使用する:
- チェックせず
テストとして、タグリファレンスへのリンクを貼ってみます。
MovableType.jpの記事に書かれていますが、初めのhttps://www.movabletype.jp/tags/まで共通、以下テンプレートタグが入っていたときに当該のリファレンスページが表示されるとのことです。あと、Open Search プラグインもアップデートと併記されていますね。
たまにテンプレートタグ検索を選択しているのを忘れてて普段ののキーワード検索をそのままやってしまうはおそらく私です。
【追記:2008/09/07】使っているボタン画像だけ置いておきます。config.yamlのソースは既存のものに追加するなどして使います。
追記:2013/04/18 URLの戻り値をmt接頭辞なしに合わせるようにしました。
- Comments
- TrackBack Closed
EntryCategoriesタグを改良するプラグインを使ってフォルダ一覧のリストを表示
- 2008年9月 1日 19:44
- Last update: Sep 01, 2008 19:46
- mt4

The blog of H.Fujimotoさまにて公開されている、EntryCategoriesタグを改良するプラグインを使って、ウェブページが属しているフォルダの一覧を表示させるためのウィジェットを試してみました。
プラグインの入手とインストール
The blog of H.Fujimoto の壱さま提供のプラグインです。以下ページにダウンロードならびにインストールの説明があります。
ダウンロードしたファイルを解凍してできた、「EntryCategoriesEx」フォルダをフォルダごとMTシステムのディレクトリのpluginsディレクトリにアップロードでインストールは完了です。
ウィジェットの作成
ウィジェットテンプレートを新規に作成します。テンプレート名はFolder Linkとしました。これは任意で自分がわかる名前でよろしいかと。
ウィジェットの本体はVicunaテンプレートにあわせた形で以下のようなものです。ulエレメントにはclass名は適当なものです。
<mt:If tag="FolderLabel">
<MTPageFolderEx>
<dt class="widget-header">List of <$MTFolderLabel$> folder</dt>
<dd>
<MTPages>
<MTPagesHeader><ul class="folderList"></MTPagesHeader>
<li><a href="<$MTPagePermalink$>"><$MTPageTitle$></a></li>
<MTPagesFooter></ul></MTPagesFooter>
</MTPages></dd>
</MTPageFolderEx>
</mt:If> ウィジェットの設定とインクルード
ウィジェットのキャッシュ設定
説明によりますと、MT4.2において、上記ウィジェットには以下のような設定をしておくとのことです。
参考
テンプレートの設定を展開させて、「作成または更新後に無効にする」を選択して「ウェブページ」と「フォルダ」にチェックを入れます。
ウィジェットをインクルード
インクルードさせたいところに、ウィジェットをインクルードさせるコードを挿入します。Vicunaテンプレートだと、ユーティリティの<dl class="navi">のあたりに。
インクルードするためのコードは壱さんのページに書かれていますが、以下のようなコードです。
<MTIfArchiveType archive_type="Page">
<MTPageIfFolder>
<MTSetVarBlock name="page_folder_id"><MTPageFolderEx>page_folder_<$MTFolderID$></MTPageFolderEx></MTSetVarBlock>
<$MTInclude widget="Folder List" key="$page_folder_id"$>
</MTPageIfFolder>
</MTIfArchiveType>ページ自体が少なくてアレですが、このような結果になりました。
このエントリは以下のページを参照しました。
- Comments
- TrackBack Closed
- Feeds
- Elsewhere
- logo